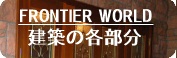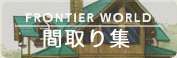ログハウス・注文住宅・輸入住宅「レッドシダー」の木の家・フロンティアワールドを知るにはこちら!

家を考える①
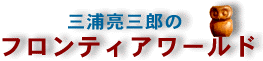 |
| エッセイ - 家を考える - |
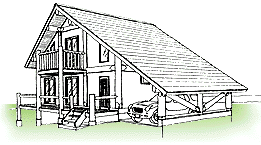 |
みうら・りょうざぶろう 1942年2月、青森県弘前市生まれ。北海道大学獣医学部卒業。実兄の三浦雄一郎とともに、広くスキービジネスに携わった後、1982年、カナダでログビルディングの技術を習得。帰国後、日本初のスクールを開校、ログハウス産業の基礎づくりに貢献。1990年、日本ログハウスフォーラムを結成。初代会長を務める。(株)フロンティアワールド社長。 著書に「ログハウスのつくり方」「ログハウス専科」がある。 |
 |
1 2 3 4 |
| 家づくりの舞台裏 |
電気屋がテレビを売る、叉は車屋が車を売る。そんなでき上がった商品を売るのに比べ、家を建てる仕事は格段にスパンが長い。最初のラフプランの段階から、設計、着工、完成まで、どんなに短くても9ヶ月から1年はかかる。土地探しからお付き合いすることも多い私の場合は、2年、3年がかりという例も珍しくはない。 |
| 千葉のK邸 |
Kさんがホームページで私の会社を知り、Eメールを通じてアプローチをしてきたのは、去年の5月14日のことだった。 |
| 家はプランニング次第 |
土地の問題が意外に長引き、本格的にプランニングに入ったのは12月に入ってからだった。できる限り詳しく考えを引き出して、それを形にしていくのが設計者の役割である。オーナーの希望を満たすプランを作るには、やはり相当な経験と能力を必要とする。 |
| K邸の建設 |
2月27日、ぎっしり詰められた41フィートコンテナ2本が到着。幸い敷地が広いので、すべての部材を建物の周囲に置くことができた。想像以上のボリュームに、Kさんは目を丸くし、太い重量感あふれる丸太を見ては目を輝かせている。 |
1 2 3 4 |
次ページ |